先週からちょっと病気になってしまっているんですが、リハビリで小文を書いてみようと思います。
自分は零細企業の経営者を長くやっているし、家庭は崩壊してしまったので、いろいろな「制度設計のモデル」から完全に外れている存在になっています。だから、日本の社会をはすから見ることになっているわけですが、ヤバいなと感じることはいくつもあります。
・厚生労働省が定めている栄養摂取基準が正しくない。そのために成人病患者の増加が止まらない。
「食事バランスガイド」について|厚生労働省
・同じ理由で管理栄養士の知識が正しくないから、患者を治せずに医療費が増大し続ける。
・医療プロトコルにはビッグファーマの影が色濃く、また日本の医学研究は「不正大国」として海外から非難されている。
サイエンス誌があぶり出す「医学研究不正大国」ニッポン(榎木英介) – 個人 – Yahoo!ニュース
という感じで、アカデミアの世界もその先にあるお役所も、頭を抱えたくなるような状態だなと思っています。
つい健康の話をしてしまいましたが、これから書こうとしているのは、そうではなくて、日本の会社組織のあり方がこれから大きく変わるぞ~、それでさらにヤバいことが起きそうだ、という、無責任な予言みたいなものです。
小熊英二さんの「日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学 (講談社現代新書)」という本に書いてあるみたいですが、日本の世帯には大きく分けて3種類あるとされています。
1:大企業勤務者の世帯。老後は比較的安定しているが、地域ネットワークがらは疎遠で孤独になりがち。
2:地元型の世帯。多くは農林業従事者。大都市以外に住み、広い持ち家があり住居費が不要な多世代同居世帯。相互扶助の中で生きるが公的補助は薄い。
3:それ以外の非正規雇用者など。自宅を保有せず、大都市とその周辺に居住し、公的補助・地域ネットワークの恩恵もどちらも受けにくい類型。
従来、3の類型は多くなかったので、日本社会の制度設計は日本の世帯は1か2に属すると仮定して設計されていることが多いようです(年金制度など)。
それで、上記書籍によれば、世帯の類型別の比率は、大企業型が26%、地元型が36%、その他が38%だそうです。なんと、(自分から見た)世間でスタンダードとされている類型は4分の1しかないじゃありませんか。
それで、自分は子どもが3人いてそろそろ就職活動かなんかもはじまっているんですが、普通はその4分の1の生き方に最初から絞って活動をするわけですよね。したがって、大学での学びというものも、その4分の1に対してのものがメインになるのでしょう。また、都会にある社会人向けの講座(大学院大学とか)というと、その4分の1の世界の人が先生なんだから、これまた限定された世界ですね。
それで、例によって壮大な前振りですみませんが、この25%の人がさらに半分になって、半分は実質的に3番目のその他に強制移管されるという試みが、すごい勢いで進んでいることを指摘しておきたいと思います。
念頭にあるのは、Salesforceに代表される、SaaSで提供されるSFAソフトウェア(Sales Force Automation)です。乱暴な説明ですみませんが、それはどういうものかというと、
「Salesforceを使って営業活動のあらゆる行動をデータ化して一元管理して、Salesforceの秘伝のタレ的な営業支援メソッドに沿って、指示通りにコトを進めていけば営業効率が抜群に上がるし、またデータ化されているから働く場所も問わないよ!」
ってなものなわけです。
世界No.1 CRM・SFA – Sales Cloud | セールスフォース・ドットコム
これが今「働き方改革」なるラベルが貼られることによって、爆発的に大企業に入りはじめています。要するに、今までよくわからなかった営業のスキルや、適当だった勤怠管理や、ムダの多かった会議や情報共有を、SaaSのソフトに全部突っ込んで解決しちゃおうよ、それが働き方改革を実現する近道だよね!ということです。
こうして、日本企業は続々と、自らの企業を「デジタル時代に再構築する」ことを放棄して、SalesforceをはじめとするSFAなどを導入することでお手軽に済ませようとしています。
地方の活力は衰退する一方ですから、一部の大企業を目指して多くの人が大都市圏に住みます。ですが、こうしたSaaSツールのおかげで、フルタイム社員ばかりにはなりません。SFAのAIが出す指示は正確で、これまでのダラダラした仕事スタイルよりも格段に業務効率が上がってしまうため、従来ほどの人数がいらないからです。
また、すべてのデータはクラウドにありますから、PCやスマホがそれをディスプレイすれば仕事ができます。だから、働き方自体が変わってしまって、大企業の中で大きな二分化が発生します。日本の社会はよく、大企業と下請けの2層構造になっているなどと言われますが、下請け企業は衰退し続け、大企業がこうしたデジタル化を背景に「自ら二層化」する世界がやってきます。
以下、現在進行系で起きていることを、フィクションを交えて誇張して書きます。
大企業がクラウドに構築したシステムによって、会議は減り、営業活動も直行直帰がメインとなって、会社はフリーアドレスとなり、面積が減りました。
中途半端な支社はクローズされ、かわりにターミナル駅の近くのシェアオフィスの利用が提案されました。個室相当の場所があれば自宅勤務でもいいという制度も作られます。商談の予約はシェアオフィスだけでなく、大手ホテルチェーンが提供するラウンジや応接ルームの利用も推奨されています。
会社にあったパブリックスペースはこうして急激に外注先の利用に変化しました。予約は営業のアポに応じてクラウドのAIがやってくれるので、社員はその指示に沿うだけです。ランチの提案までしてくれるのには驚きました。
こうして、大企業に勤めながらも、「席のある人」と「席のない人」の分断化が進みました。給料はそれほど違わないのかもしれませんが、どうも「席あり派」の方が出世に直結していそうで、長期的には、席なし派は仕事以外の生きがいを見つけないといけなくなりそうです。
こうして急激に儲かっていったのがSFAやCRMなどを提供するSaaSベンダー。そして、これらに対して働く空間を提供する新しいタイプの不動産ベンダーです。
従来は「貸会議室」「高級ホテル」「ビジネスホテル」「ラウンジ」「カフェ・喫茶店」「コワーキングスペース」「シェアオフィス」「カラオケルーム」などとそれぞれの業態であったものが、「仕事場を提供する」という切り口で融合して、それらをAIを使って束ねて企業に販売するオンラインの「配室エージェント」が生まれ、大手ホテルチェーンやOTA(Online Travel Agent)などが入り乱れて覇を競うようになります。
こうした徹底した効率の追求は、「働き方改革」の錦の御旗のもとにバラ色の未来として進められるわけですが、新しい形での社会の分断化をより進める可能性も高いでしょう。だって、先ほど言った、大企業は4分の1という部分が、こうして2つに分断されて8分の1になってしまったら、それを「前提」としている教育や社会の制度設計は、もうほとんど意味のないものに成り下がってしまうからです。
それに、SFAが社会制度に及ぼす影響を研究している研究者なんていないみたいだし(いらしたらお会いしたいので教えてください)。すでに「意味のないもの」になりつつあるひとつの現れだよね。
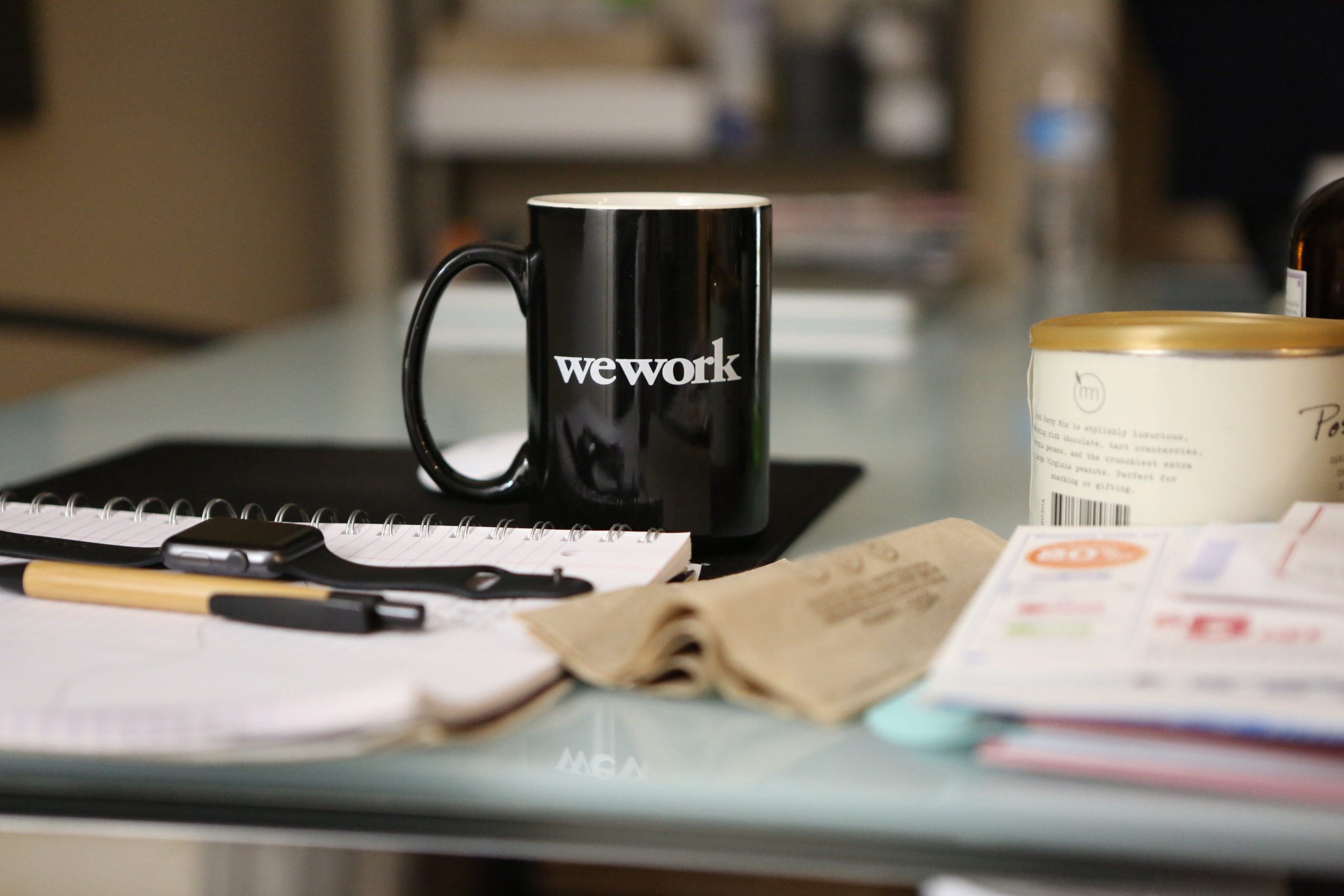
なんかひとり語りになっていますが、こうした新しい社会の仕組みができようとするときには、それに乗じて無理な金儲けをしたがる資本家サイドと、それを封じ込める真っ当な枠組みを提供する法規制とのせめぎ合いが生じるのでしょう。
カリフォルニア州で成立する「議会法案第5号(通称AB5)」は、日本で言う働き方改革や彼の地ではギグ・エコノミーと言われる勤務形態に混ざり込んでいる、フリーランスと雇用契約を悪意に混同した就業スタイルにストップをかけるもののようです。
このAB5では、SFAのような管理や指示を目的としたSaaSツールで仕事をした場合には、それが自営業者とはみなされないように基準を定めているように見えます。
via: ギグエコノミー、ついに法で規制 米カリフォルニア州で新法成立へ | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)
上記のAB5に関する解説記事です。
ウーバーを脅かすカリフォルニアの画期的新法 ドライバーも配達員も「請負」から「従業員」へ | JBpress(Japan Business Press)
今朝、日経ビジネスを読んでいたら以下のような記述があったのでメモしておきます。それでその21世紀型っぽい大学ってのは、結局には日本にはないのかな?
via:[議論]野口悠紀雄「大学を『21世紀型』に移行せよ」 (2ページ目):日経ビジネス電子版
野口さんが言っているABCは僕の親記事に全部要素として入っているね。B(ブロックチェーン)のことは言葉としては入っていないけれど、SFAがお金の流れに直結しているのは自明だから。