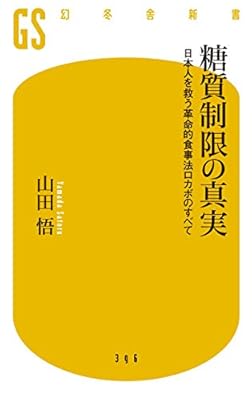糖質制限の実践とその劇的な効果 – 1
本連載は「旅を通して転移がんを克服した全記録」です。(編集担当:resortboy)
何ごとも極端にやると、どこかにしわ寄せがきますね。特に、ごはんやパンを抜く「糖質制限」は、私にとって全く未経験のものでした。そこで、無理なく出来る範囲で「適当」に実行してみて、様子を見ながら進化させていく。そんな感じで私の「プチ糖質制限生活」ははじまりました。
2度目のがん手術から6年
私が糖質制限を始めたのは2014年10月でした。2度目のがん手術から、すでに6年が経っていました。その6年の間、一度もがんセンターに行っていませんので、体内のがん細胞がどうなっているのか、「誰も」知りません。
孤立無援のがん治療中でしたが、体調は非常に良好で、国内・海外の旅行を大いに楽しんでいました。
今回の話題である糖質制限については、多数の書籍が出版されており、その内容も多岐にわたっています。その中で、私は次の2冊の書籍を参考に実践を開始しました。
主食をやめると健康になる 糖質制限食で体質が変わる!(江部康二、ダイヤモンド社、2011年11月)
糖質制限の真実 日本人を救う革命的食事法ロカボのすべて(山田悟、幻冬舎新書、2015年11月)
ゲルソン療法は糖質過多だった
私のがん対策のスタートは自己流の「ゲルソン療法」でした。
ゲルソン療法は大量のニンジン・野菜ジュースと無塩食が特徴ですが、脂肪とたんぱく質の摂取を制限し、未精白の穀類(炭水化物)と野菜の摂取を薦めていました。
そこで、私は従来の白米をやめ、無農薬・有機栽培の玄米をネットで調達し、朝・昼・夜と、茶碗1杯の玄米を食べました。また外食の時は、ラーメンやうどんをやめて「そば」にしました。パンも同様です。白い食パンの代わりに全粒粉パンにしました。
「全粒穀物主義」のような感じでしたが、昔からある玄米菜食主義とか、マクロビオティックのような、流儀の深入りはしてはいません。主食の炭水化物を全粒穀物に変えただけです。
ところで、糖尿病の患者さんならよくご存じの「グリセミック指数(GI値)」というのがあります。食品ごとに血糖値の上昇度合いを示した数値で、ブドウ糖が100に当たります。70以上なら高GI、55以下が低GIとして分類されています。
白米のGI値は88と非常に高いため、食後に血糖値が急激に上がります。一方、玄米のGI値は55と低く、血糖値の上昇リスクは少ないです。玄米には食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれており、白米より健康的な食材と見なされています。
しかし糖質制限という観点から見ると、玄米は決して推奨されないものです。茶碗1杯の白米と玄米の糖質量の差はわずか2gです(日本食品標準成分表2020年版(八訂)より)。
私は、健康によいと思って1日3食、茶碗1杯の玄米を食べてきたのですが、糖質量は合計165gにもなります。これはミニ角砂糖なら55個分に相当し、白米でも玄米でもほぼ同じです。
さらに、大量のニンジンジュースが問題でした。ニンジンはGI値が80と非常に高く、食後血糖値が急激に上昇します。これを大量に摂取するゲルソン療法は、完全に糖質過多の食事でした。
糖質制限食は糖質を抜く(または少なくする)代わりに、脂質やたんぱく質をたくさん食べます。これもゲルソン療法とは正反対です。ちょっと困ったことになってきました。
しかし、これまで数々の書籍で糖質制限を学んだ私は、がんへの勝利、そしてダイエット成功のためには、「糖質制限をやるしかない!」という気になっていました。
(続く)
【次回】第34回・糖質制限の実践とその劇的な効果 – 2
【前回】第32回・ケトン体回路を起動せよ!- 3
本連載が単行本(紙の書籍)として刊行されました
(本連載記事一覧)がん患者よ、旅に出よう!
(スペシャル対談)私のリゾートライフの全体マップ
(筆者ホームページ)舟橋栄二「第二の人生を豊かに」